母の教え
「若い時の苦労は買ってでもしなさい。」
母親の教えの中で、今でも心に残っているものの一つだ。はて、どのような機会に母が語ってくれたのか思い出せない。末っ子で甘やかされて育ったので、苦労などというものとは縁のない子ども時代を送ったからだ。そしてそのことが、つまり成人まで何の苦労もしなかったということが、私にとってある種”コンプレックス”でもあったからだ。世の中でしかるべき仕事をなしえる人、なしえた人には、貧しい、あるいは厳しくしつけられた幼年時代をおくったという人が多い。
山口県「萩」へ
東萩駅に着いた時はすでに暗かった。東萩というくらいだから萩中心部の東端にある。駅を出て川を渡ると萩市の中心である。地形的には阿武川の河口にできた三角州地帯がそれになる。予約したホテルは地図で見るとこの三角州の中心部にあったが、橋を渡ってほんの数分で到着してしまい、やや拍子抜けがした。

山口県萩市中心部
それほど小さい町なのだ。歩いた感覚でいっても三角州そのものは長い部分をとっても直線で3キロ程度ではないのか。今、改めて航空写真を見てみると、ちょうど三角州の中心に江戸時代の藩校「明倫館」、その西の野球場がかなり大きく見えるのでおおよその大きさはイメージできるだろう。その小さい三角州プラスアルファの地域が、幕末、松下村塾の吉田松陰をはじめ、高杉晋作、木戸孝允、久坂玄瑞、伊藤博文などなど、日本人なら名前を聞けばたいてい知る明治維新の主人公たちを生み出した。

松下村塾 講義室
世に棲む日日

玉木文之進(1810-1876年)
萩へ来て、いちばん訪れてみたかったのは、玉木文之進の旧宅。幕末の長州人としてはやや知名度は劣るが彼は吉田松陰の叔父であり松陰の幼年期の教育役。有名な松下村塾は吉田松陰が作ったものではなく、玉木文之進が始めた。吉田松陰は玉木の松下村塾を引き継いだことになる。
「世に棲む日々」は好きな作品である。司馬遼太郎の作品の中で何度も繰り返し読んだというものはこれしかない。冒頭に近い部分に玉木文之進の紹介がある。筆者が司馬遼太郎の作品の中で個人的に最も印象的であり、絵画のようなイメージで記憶している部分が、玉木文之進が幼少の吉田松陰を教育する以下のくだりである。
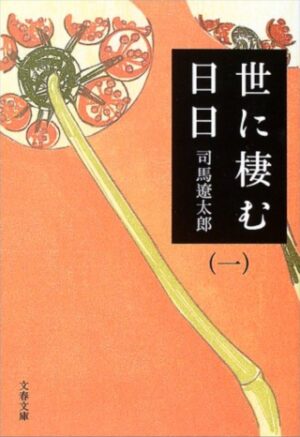 ある夏のことである。その日は格別に暑く、野は燃えるようであった。暑い日は松陰は大きな百姓笠をかぶらされた。この日もそうであったが、しかし暑さで顔じゅうが汗で濡れ、その汗の粘りに蠅が集って堪らなく痒かった。松陰はついに手をあげて搔いた。これが文之進の目に留まった。折檻がはじまった。この日の折檻は特に凄まじく、「それでも侍の子か」と声をあげるなり松陰をなぐりたおし、起き上がるとまた殴り、ついに庭の前の崖へ向かって突き飛ばした。松陰は崖からころがりおち、切り株に横腹を打って気絶した。(死んだ)と、母親のお滝はおもった。(中略)このとき、(お滝は)文之進にきこえぬよう、小声で、ちょうど祈るように、「寅や、いっそお死に。死んでしまえばいいのに」とつぶやきつづけた。 「世に棲む日日」 玉木文之進から
ある夏のことである。その日は格別に暑く、野は燃えるようであった。暑い日は松陰は大きな百姓笠をかぶらされた。この日もそうであったが、しかし暑さで顔じゅうが汗で濡れ、その汗の粘りに蠅が集って堪らなく痒かった。松陰はついに手をあげて搔いた。これが文之進の目に留まった。折檻がはじまった。この日の折檻は特に凄まじく、「それでも侍の子か」と声をあげるなり松陰をなぐりたおし、起き上がるとまた殴り、ついに庭の前の崖へ向かって突き飛ばした。松陰は崖からころがりおち、切り株に横腹を打って気絶した。(死んだ)と、母親のお滝はおもった。(中略)このとき、(お滝は)文之進にきこえぬよう、小声で、ちょうど祈るように、「寅や、いっそお死に。死んでしまえばいいのに」とつぶやきつづけた。 「世に棲む日日」 玉木文之進から幼い我が息子に「死んでしまえばいいのに」と心の中で念ずる母親が、たった百五十年ていど前の日本にいたということが、平和な日本の平和な家庭で生まれ育った筆者の印象に残った。司馬遼太郎の好きな形容を使えば、平和ボケの目を覚まさせるような「すさまじい、情景」だ。
玉木文之進旧宅、吉田松陰像
翌日、早めにホテルを出発。三角州から少し外れるが、もと来たJR駅側にある松下村塾のある松陰神社へ。神社から少し歩き伊藤博文旧宅を過ぎると、ほどなく玉木文之進旧宅に着く。

玉木文之進旧宅
上がりこんで畳に正座してみたり、縁側に座ってぼんやりしてみたりしていると奥の小部屋からここの管理をしているのだろうか、人のよさそうなおばさんがでてきて世間話とも解説ともつかない話をしてくれた。
玉木家のあれこれを話してくれたが、内容は覚えていない。
(ちなみにこの日は2020年1月21日、コロナ禍前である。そしてこれを書いている今は2022年4月30日、上海はロックダウン真っ最中、隣接市にある大学に勤務する者として中国のいわゆるゼロコロナ政策にお付き合いの形で、多少なりと不自由な生活をしている最中である。)
どんな文脈でこの一言が彼女の口から出たかも忘れてしまったのだが、「何と言っても260年も(この萩に)閉じ込められましたからね。」そう彼女は感慨深げに語ってくれたのを覚えている。
玉木家旧邸を辞し、来た道から直角に折れ、少し上ると吉田松陰生誕の地に着く。吉田松陰、そして傍らに松陰と共に小舟で黒船に近づきアメリカに行こうとしたという金子重輔が控える像がある。松陰の視線の方向に萩の全景がある。

萩市三角州 吉田松陰、金子重輔像
「260年閉じ込められましたから」という言葉が再び頭の中をめぐり、その場所から見たあまりに狭い萩市の三角州が、長州人が藩ごと閉じ込められた牢獄のように見えた。江戸時代を260年維持した徳川家は見事だ。しかし、その徳川によって裏日本のこの天然の隔離所ともいうべき萩に閉じ込められながらも、武士である誇りを260年に渡って片時も忘れず、人材を育成し続けた伝統が吉田松陰を生んだ。
人は一度大きな成功を収めると成功体験に束縛されるあまり、やがてまっとうな判断ができなくなるものである。その意味で歴史は残酷なまでに繰り返す。そうでない例はまれにしかなく貴重だ。
しかしながら、真に人や組織を育て、飛躍を促すのは、不遇の境遇であり失敗体験である。それを跳ね返そうとする力が、やがて爆発的なものとなって時代を変えるのだ。日本を変えた明治維新は、やはりこの場所からスタートせねばならなかったのだと、妙に納得できたものだ。
若い時でなくてもよい。苦労は、やはり買ってでもしておかなくてはならないものだ。




コメント