Come Back !!
常熟での生活が始まった。仕事人生の再開である。
常熟では何のストレスもなく、やりたいことをやったと前回書いた。ブランクはあった。が不安はなかった。
ほんの2年前までは、毎朝、重い身体を無理矢理満員の通勤電車に乗せ、機械のように持ち場に向かい、亡霊のように自分の席についていた…。立ち上げたパソコンの画面を前に、ほとんどフリーズ状態になっていた自分。気が付けば昼休みの鐘が鳴り、その次に気が付くのが終業の鐘であったという毎日。
それでも自分のどこかが壊れていることにすら思い至らなかった焦燥の毎日があったことなど、他人の事のようであった。
仕事をしよう!
総経理、おはよう運動
 まずは、会社の誰よりも早く出勤した。6時半には作業服姿で玄関の掃き掃除を始める。7時過ぎに社員たちがぼつぼつと出勤してくるが、新入りの総経理として一人一人と、朝の挨拶を交わした。この習慣は総経理であった期間中、欠かさなかった。 そういう”日本的”なことはやらない方がいい、と多くの日本人は思っている。掃除はしかるべき低賃金の人間がやるもので、高単価の総経理がそういう誰でもできる作業をやるなど、そもそもコスト意識がない、というようなことをしたり顔でいう者もいる。確かにその通りかもしれない。箒で掃いてる時間があれば、その時間でもっと儲かるネタを考えたり、探してきてもらう方が、下のものとしてはありがたい。しかし、やってみれば結局ペイするのだ。要はやるかどうかである。 どちらかといえば、悪い意味での日本式浪花節的行動であることはわかっていた。最初はおはようと声をかけても、言葉を返してくれる行員はいなかった。毎日玄関で待ち構えているので、そのうち笑顔を返す人もあらわれ、ある程度の期間の後は皆と挨拶を交わせるようになった。彼らがどう感じていたかは、聞けなかった。しかしそこで生まれた連帯感はいざという時、会社を救った。 5年後、私の送別の場でその時点で会社のナンバー2であった工場長が、挨拶の席で私が毎日玄関に立って皆を迎えていたことに触れ、そのことが見えない力で私たちを一つにまとめていた、その精神を忘れずにいたい、といったようなことを言ってくれたのは、世辞とわかっていても、嬉しかった。
まずは、会社の誰よりも早く出勤した。6時半には作業服姿で玄関の掃き掃除を始める。7時過ぎに社員たちがぼつぼつと出勤してくるが、新入りの総経理として一人一人と、朝の挨拶を交わした。この習慣は総経理であった期間中、欠かさなかった。 そういう”日本的”なことはやらない方がいい、と多くの日本人は思っている。掃除はしかるべき低賃金の人間がやるもので、高単価の総経理がそういう誰でもできる作業をやるなど、そもそもコスト意識がない、というようなことをしたり顔でいう者もいる。確かにその通りかもしれない。箒で掃いてる時間があれば、その時間でもっと儲かるネタを考えたり、探してきてもらう方が、下のものとしてはありがたい。しかし、やってみれば結局ペイするのだ。要はやるかどうかである。 どちらかといえば、悪い意味での日本式浪花節的行動であることはわかっていた。最初はおはようと声をかけても、言葉を返してくれる行員はいなかった。毎日玄関で待ち構えているので、そのうち笑顔を返す人もあらわれ、ある程度の期間の後は皆と挨拶を交わせるようになった。彼らがどう感じていたかは、聞けなかった。しかしそこで生まれた連帯感はいざという時、会社を救った。 5年後、私の送別の場でその時点で会社のナンバー2であった工場長が、挨拶の席で私が毎日玄関に立って皆を迎えていたことに触れ、そのことが見えない力で私たちを一つにまとめていた、その精神を忘れずにいたい、といったようなことを言ってくれたのは、世辞とわかっていても、嬉しかった。
評価制度の見直し
出稼ぎ労働者、つまり金が目当ての工員がほとんどの会社であるから、評価制度の見直しが第一優先であった。人事評価のルールそのものが、曖昧であったので、まずは評価尺度を決め、現行の給与と無理やり連動させた。過去は評価者の匙加減であった部分もあり、工員同士で手取りを比べ合い、なぜこいつの給料は自分より多いか、というようなクレームが多かった。工員同士が殴り合いの喧嘩を始めるといったトラブルも多かったが、多くは金がからんでいた。ある程度、客観的な評価尺度を作っても、落ち着くまでは1年ぐらいかかった。

報奨制度、加点主義
 評価は、減点主義をやめ、加点主義にした。過去にはクレームやトラブルに対して罰金制度というものがあった。他の会社でも罰金制度のあるところは多かった。そこをあえて、罰金ではなく、良い行動、成績に対し表彰することにした。改善提案や勤続年数なども表彰の対象にした。原資は同じでも、分配を調整して工員には徳をしたように思ってもらえたと思う。職場のギスギス感はなくなった。想像以上に社員の入れ替わりが早かったため効果を数字で確認できるまではいたらなかった。ただ、やったことは間違いではなかったと思っている。 いわゆる5S運動というのも、始めた。自分が80年代に経験したことを、思い出し、そのままなぞるように実行しただけだったが、十分通用した。
評価は、減点主義をやめ、加点主義にした。過去にはクレームやトラブルに対して罰金制度というものがあった。他の会社でも罰金制度のあるところは多かった。そこをあえて、罰金ではなく、良い行動、成績に対し表彰することにした。改善提案や勤続年数なども表彰の対象にした。原資は同じでも、分配を調整して工員には徳をしたように思ってもらえたと思う。職場のギスギス感はなくなった。想像以上に社員の入れ替わりが早かったため効果を数字で確認できるまではいたらなかった。ただ、やったことは間違いではなかったと思っている。 いわゆる5S運動というのも、始めた。自分が80年代に経験したことを、思い出し、そのままなぞるように実行しただけだったが、十分通用した。
総経理の仕事
以上は言ってみればトップでなくてもできる仕事であったが、小さいながら総経理としては、三つ仕事をしたと考えている。
①後継者作り
第一は後継者作り。誰を次の総経理にするかは大切な仕事だ。誰がいいかは簡単であった。工場の運営は、それまで、たった一人の職人気質のベテラン社員が動かしていた。仮にCとしよう。彼にマネジメントを学ばせれば良いと考えた。ちょっとずるいやり方だったかもしれないが、私はこの仕事を本社工場に丸投げした。時期を見て彼をマネジメント研修と称して本社に留学させた。Cのワンマン体制であった工場は一時的に弱くなり私を含め幹部は苦しかった。しかし、私は経験上ある程度の規模以上の組織には、再生力があることを知っていた。Cの下にいて、力を発揮することを抑えられていた二人の若手が、ほどなくCの代役として目覚ましい働きをしてくれるようになった。
孫会社設立
第二。これは私だけの仕事とは言えないが、それまで個人で我々の工場の廃品をリサイクルし、糧を得ていた人物Nに、我々の工場の下請けをする会社を作らせた。東京本社から見れば孫受けになる。常熟の工場には30台程度の成型機があったが、Nの工場は3台からスタートさせた。独立した法人とはいえ、行ってみれば東京本社の100%下請けである。仕事の量には波があり、安定しない。季節ごとに従業員の数を調整する必要があった。この不安定さの受け皿をNが受け持ってくれた、緩衝材(バッファー)としての効果は計り知れなかった。 以上のこと、方針を最初の3か月でやり終えた。
いよいよ本丸へ
 そして今の生活につながる第三の仕事のきっかけは2012年5月に訪れた。じつはこのことは常熟赴任前、本社の幹部に相談、了承済みのアクションであった。格好良く言えば“教育事業への参入”、まずは常熟に小さな語学教室を作り、開発区に駐在する日本人に中国語を、日系企業で働く地元の中国人を中心として、彼らに日本語を教える場所を作った。そのあたりのやり方、経緯については、長くなるので回をあらためてまとめたいと思う。単にラッキーだったと思えるようなことが、何度か重なり、こんな私でも雇われ社長ではなく、規模は極小ながら自分の城のようなものを作ることができた。13年11月、常熟小葵花教育信息有限公司設立、14年5月開業、とトントン拍子に進んだ。
そして今の生活につながる第三の仕事のきっかけは2012年5月に訪れた。じつはこのことは常熟赴任前、本社の幹部に相談、了承済みのアクションであった。格好良く言えば“教育事業への参入”、まずは常熟に小さな語学教室を作り、開発区に駐在する日本人に中国語を、日系企業で働く地元の中国人を中心として、彼らに日本語を教える場所を作った。そのあたりのやり方、経緯については、長くなるので回をあらためてまとめたいと思う。単にラッキーだったと思えるようなことが、何度か重なり、こんな私でも雇われ社長ではなく、規模は極小ながら自分の城のようなものを作ることができた。13年11月、常熟小葵花教育信息有限公司設立、14年5月開業、とトントン拍子に進んだ。
(続く)


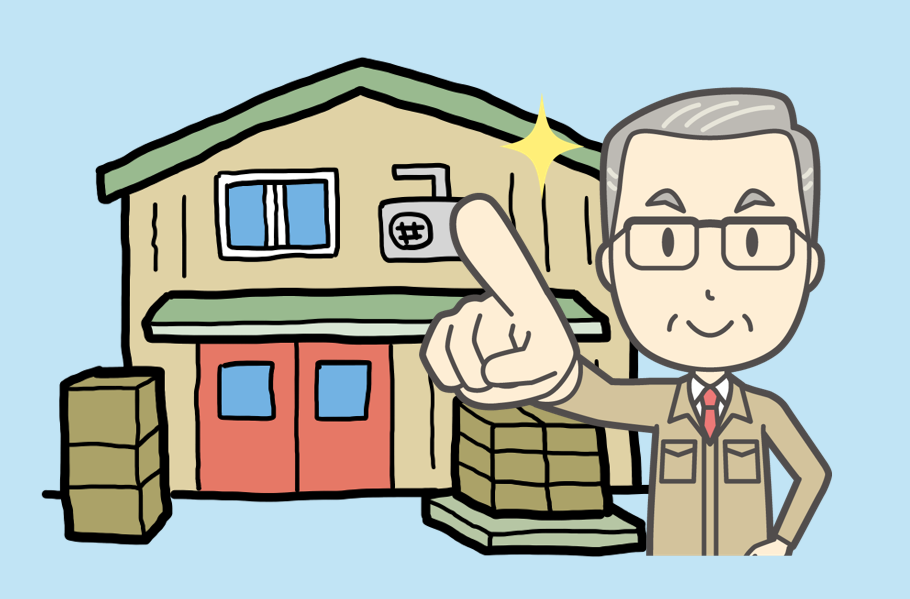


コメント