関ケ原の戦い(1600年)その後
1600年天下分け目の関ヶ原の戦いに戦勝した徳川家康は、1603年に江戸に徳川幕府を開く。関ヶ原の戦いでは、全国の大名が東西に分かれて戦ったが、家康は戦いに勝利した後、全国の大名を再編成した。各大名を将軍との信頼関係で親藩・譜代・外様の三つに分けた。親藩は徳川氏一門の御三家(尾張・紀伊・水戸の徳川家)、譜代は古くから徳川の家臣であった大名、外様は関ヶ原の戦い前後に徳川に服従した大名である。当然外様への待遇は悪く、とりつぶしや遠隔地への配置換えが行われた。
毛利家の処分
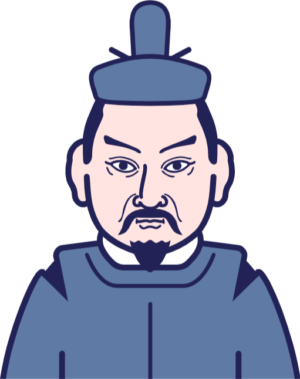
毛利輝元(1553-1625年)
もっとも厳しい処分を受けたのが、関ケ原の戦いで西軍の総大将であった毛利輝元。戦国期の毛利氏と言えば、もともとは安芸の国(広島)を中心に中国地方全域の覇者であった。当初、家康はこの藩を潰そうとした。しかし毛利家の分家で、関ケ原で家康に内通し功をなした吉川(きっかわ)氏が毛利家を救った。吉川氏は、家康の毛利家とりつぶしの意志が固いと知ると、「自分の頂戴すべき防長二州を毛利本家にお与えください」と進言。なんとか聞き入れられた。結果的に、家康のこの温情が265年続いた徳川家康を滅ぼすことになるのだが、それは後の話。
とはいえ、かつて中国地方に覇を唱えた毛利氏ともあろうものが、防長二州、つまり現在の山口県に押し込められた。しかも城は山口ではなく、裏日本の萩に置けとまで指示された。当時の萩は阿武川の小さな三角州であり、人の住まない湿地帯だった。毛利はここに指月城を築き、街をつくった。生活も困窮したであろう。彼らにとっては、温情を感じるどころか、憎しみがますます増大したことだろう。

中国地方
家康の誤算
自己保存の知恵と用心深さにかけては、天才的ともいえた家康であったが、毛利家の処分についてはあきらかに失敗した。しかしながら失敗したことを自らわかっており、臨終の時にも、刀を振り上げ、「我が遺骸は西に向かって埋めよ。死すとも西に向かいこの刀で皆を守る。」と遺言したという。家康の心残りは、潜在的国としての長州毛利氏、そして同じく外様の薩摩の島津氏であった。
ついでながら、現在日本で美しい天守閣を持ち、観光名所になっているところと言えば、別名白鷺城ともいわれる姫路城、大阪のシンボルともいえる大阪城、そして名古屋城あたりだが、この三つの城は、徳川家康の仮想敵国であった長州藩が江戸の攻めあがってきた場合の、守りの要所の城として増強された城なのである。

吉田松陰(1830-1859年)
果たして、明治維新は長州、薩摩を中心に成し遂げられた。維新の起爆剤となったのは長州藩である。萩の小さな三角州に押し込められた毛利氏の子孫は265年間、徳川に対する怨嗟を世襲し、ついには日本の政体を転覆させ、新しい日本を作ることに成功したのだ。
幕末、萩の三角州には奇兵隊を結成し、頓挫しそうになった維新の力を復活させた高杉晋作、維新三傑の一人、桂小五郎、初代総理大臣をつとめた伊藤博文、陸軍の長であり総理大臣もつとめた山縣有朋がいた。そして彼ら明治の立役者には共通の師、吉田松陰がいたのである。吉田松陰は私塾松下村塾において、多くの明治の日本を主導した塾生をそだてたのである。
吉田松陰とはいかなる人物か。では彼の故郷萩を訪ねるところから始めよう。
山口県「萩」へ
萩へは通常JR東萩駅から入る。三角州である萩城下町の東にある。駅を出てすぐ川を渡るとすでに三角州の中。私たちが予約したホテルは地図で見るとこの三角州の中心部にあったが、橋を渡ってほんの10分で到着してしまい、やや拍子抜けがする。

山口県萩市中心部
それほど小さい町なのだ。歩いた感覚でいっても三角州そのものは長い部分をとっても直線で3キロ程度ではないのか。改めて航空写真を見てみると、ちょうど三角州の中心に江戸時代の藩校「明倫館」、その西の野球場がかなり大きく見えるのでおおよその大きさはイメージできるだろう。この小さい三角州プラスアルファの地域が、幕末、松下村塾の吉田松陰をはじめ、高杉晋作、木戸孝允、久坂玄瑞、伊藤博文などの、日本人なら名前を聞けばわかる明治維新の主人公たちを生み出した。
玉木文之進(1810-1876年)
吉田松陰の幼年時代を知るため、玉木文之進の旧宅を訪れる。玉木は吉田松陰の叔父であり松陰の幼年期の教育役。有名な松下村塾は吉田松陰が作ったものではなく、実際は玉木文之進が始めたようだ。吉田松陰は玉木の松下村塾を引き継いだことになる。
「世に棲む日々」の冒頭に近い部分に玉木文之進の紹介がある。筆者が司馬遼太郎の作品の中で個人的に最も印象的であり、絵画のようなイメージで記憶している部分が、玉木文之進が幼少の吉田松陰を教育する以下のくだりである。
ある夏のことである。その日は格別に暑く、野は燃えるようであった。暑い日は松陰は大きな百姓笠をかぶらされた。この日もそうであったが、しかし暑さで顔じゅうが汗で濡れ、その汗の粘りに蠅が集って堪らなく痒かった。松陰はついに手をあげて搔いた。これが文之進の目に留まった。折檻がはじまった。この日の折檻は特に凄まじく、「それでも侍の子か」と声をあげるなり松陰をなぐりたおし、起き上がるとまた殴り、ついに庭の前の崖へ向かって突き飛ばした。松陰は崖からころがりおち、切り株に横腹を打って気絶した。(死んだ)と、母親のお滝はおもった。(中略)このとき、(お滝は)文之進にきこえぬよう、小声で、ちょうど祈るように、「寅や、いっそお死に。死んでしまえばいいのに」とつぶやきつづけた。 「世に棲む日日」 玉木文之進から
(続く)





コメント