1953年ペリー来航、開国要求
最近読んだ本の中で、日本人なかなかすごいね!と、いたく感銘を受けた部分がある。岩波新書日本近現代史シリーズの「幕末・維新」の巻(井上勝生著)の中で、ペリー来航から開国にいたる記載の中で、ペリー艦隊の乗組員たちと一般の江戸庶民がどのように交流していたかというくだりである。
ペリー来航というのは、1953年ペリー率いる艦隊が浦賀沖に突如現れ、翌54年、長く鎖国状態にあった日本を開国させた日本史上の重要事件である。日本人は小学校の歴史で習う。
という狂歌が知られている。上喜撰とは高級緑茶の名前で「蒸気船(じょうきせん)」とかけている。四杯も飲めば寝られなくなるということと、4隻の異国の軍艦がやってきて太平の世の人々の不安をかきたてたという意味を重ねている。
250年余り続いた江戸時代は、戦争のない安定した時代ではあったが鎖国政策で海外との積極的な交流を絶ったため、日本が西欧列強に比べ大きく後れをとっていた。開国とそれに続く明治維新によって日本は眠りから覚め、近代国家建設へまい進する、というのが教科書的解説である。そのような歴史観の中に我々はいる。
しかし「…」なのである。この「…」の部分を言いたい。
「ペリーの横浜上陸」を描いたハイネ
「ペリーの横浜上陸」という絵は中学、高校の教科書にほぼ100%載っているもので日本人にはなじみが深い。

ペリーの横浜上陸

Wilhelm Heine、1827-1885年
この「ペリーの横浜上陸」という絵、ペリー艦隊に同行した画家のひとりハイネ(Wilhelm Heine、1827-1885年)によって描かれたものという。当時は写真というものがまだまだ普及していなかった時代で、画家は艦隊の記録係という位置づけで、多くの絵を描いた。
井上勝生先生の「幕末・維新」では、ペリー艦隊の水兵、将官たちと日本の庶民との交流の様子が、ハイネの描いたさまざまな絵と共に紹介されている。
それによるとどうも当時の日本人、特に庶民の姿は従来考えられていたような、”後進民族のそれ”とは違うようだ。
従来のイメージとはこういうものだ。鎖国という「閉じた社会」から外を見た時、日本国民にとって欧米の人々は嫌悪と警戒の対象であった。その感情が明治以降日本人に植え付けられた欧米への後進意識、劣等感につながっている。卑屈さと恐れの混じった眼でアメリカ人を見ていたのではないかということだ。
もちろん劣等感はあったろう。その劣等感が、負けるものかと日本の近代化を加速し、大ざっぱに言えば1970年80年代の経済大国日本へとつながる大きなドライビングフォースであったことは間違いない。
ハイネ作「下田の公衆浴場」
しかし、実際のところ江戸後期の人々、すくなくとも一般庶民はそのような劣等感とは無縁であったらしい。以下「幕末・維新」から抜粋するが、庶民、とりわけ江戸の女性は訪れた欧米人の多くが絶賛している。
- 「陽気で、純朴にして淑やか、生まれつき気品にあふれている。」(ヒュブナー)
- 「感じがいいのだ。」「物おじしない。」(ベルク)
- 「中国の女性と違う。いささかの恐怖の気おくれも示さない。」(フォーチュン)
圧巻は、画家ハイネ自身が実際に入って描いた「下田の公衆浴場」(下図)であり、ハイネをして「外人が入ってきても、この裸ん坊たちは、一向に驚かない」と言わせた江戸庶民の開放性である。

下田の公衆浴場
(先の「ぺリーの横浜上陸」もそうだが、細部にわたり描写がていねいで、見ていて飽きない絵である。)
その後置かれた江戸のアメリカ領事館に赴任したハリスも同じく下田の銭湯で次のような経験をしたという。
私は、子供をつれて湯に入っている一人の女を見た。彼女は少しの不安げもなく、微笑みをうかべながら私に、いつも日本人がいう「オハヨー」を言った……
(中略)
同じころ、ハリスは下田を散歩して、次のように言う。「容貌に窮乏をあらわしている一人の人間をも」見ていない。「子供たちの顔はみな「満月」のように丸々と肥えているし、男女ともすこぶる肉付きがよい。彼らが十分に食べていないと想像することはいささかもできない」と。
「幕末・維新」井上勝生著から
男女混浴で、外国人が入ってきても恥ずかしがらないということが、なぜ「日本人すごいね!」という発想につながるのか不思議に思う人も多いかもしれない。
そのあたりうまく説明できない。しかし(ちょっと飛躍するが)世の中を、金とか、力とかもっと言えば覇権とかパワーバランスとか、そういうものでしか把握できないとする現代的な尺度とは、全く別の次元に、江戸時代の日本の大半は、あったのではないかと思う。西欧の権威に対して全く物おじしない態度というのが、それを示しているように思うのだ。
 教科書で語られる歴史の陰に、正史では語られない史実や人類が選ぶべきであった別の可能性があったに違いない。今からほんの170年前の日本人が当たり前に持っていた”日本人らしさ”というのは、どのような価値観に基づくものだったのか?そしてその価値観は、開国とか近代化とかと引き換えに簡単に手放してよいようなものだったのだろうか?
教科書で語られる歴史の陰に、正史では語られない史実や人類が選ぶべきであった別の可能性があったに違いない。今からほんの170年前の日本人が当たり前に持っていた”日本人らしさ”というのは、どのような価値観に基づくものだったのか?そしてその価値観は、開国とか近代化とかと引き換えに簡単に手放してよいようなものだったのだろうか?
江戸時代に限らない。いい意味でも悪い意味でもグローバル化してしまい、ややもすれば価値観が均質化してしまいそうな現代。歴史の断片からでもいい、日本人が本来持っている普遍的な日本人像を見つけ出してみたい。私はそんなことをずっと考えている。
「幕末・維新」井上勝生著 「はじめに」から
実は表題の本には「はじめに」を見ておおいに引き込まれるものがあった。
筆者の歴史観とでもいうのだろうか。そういうものを感じ取ることのできる名文だと思った。
和暦で嘉永五年、陽暦の1852年2月、日本を開国させる使命をあたえられたペリーは、アメリカ東部の海軍基地を出発し、大西洋を横断、アフリカ大陸西岸を南下し、ちょうど二か月後、年が改まった53年1月下旬に大陸南端の、イギリス植民地だったケープタウンに入る。本書の最初の主題である江戸湾の浦賀へ投錨するのは、さらにその5か月後である。
『ペリー提督日本遠征記』の、この大西洋からインド洋へと航海するあたりは、欧米の植民地にされたアフリカやアジアの諸民族の様子がじつに興味深く描かれている。南アフリカの部分を紹介しつつ、本書の序言にかえよう。
コーサ族の首長夫人
1853年の南アフリカは、50年から始まっていたイギリスと南アフリカ諸部族とのムランジェニ戦争がイギリスの勝利に帰していた。ペリーは牢獄に捕らえられたコーサ族の首長夫妻を訪問し、会見する。武運つたなく、妻や属僚とともに捕虜となった首長は、20代半ばの立派な容貌の青年であった。画家ブラウンが描いた首長夫妻の肖像のうち、夫人の肖像を上に掲げた。『ぺリー提督日本遠征記』の図版のなかで格別に印象に残るものである。気品があり、深い憂愁が伝わってくる。このコーサ族の子孫の一人が、南アフリカ共和国の反アパルトヘイトの不屈の運動家、後に大統領となったマンデラである。
シリーズ日本近現代史「幕末・維新」井上勝生著 序文から
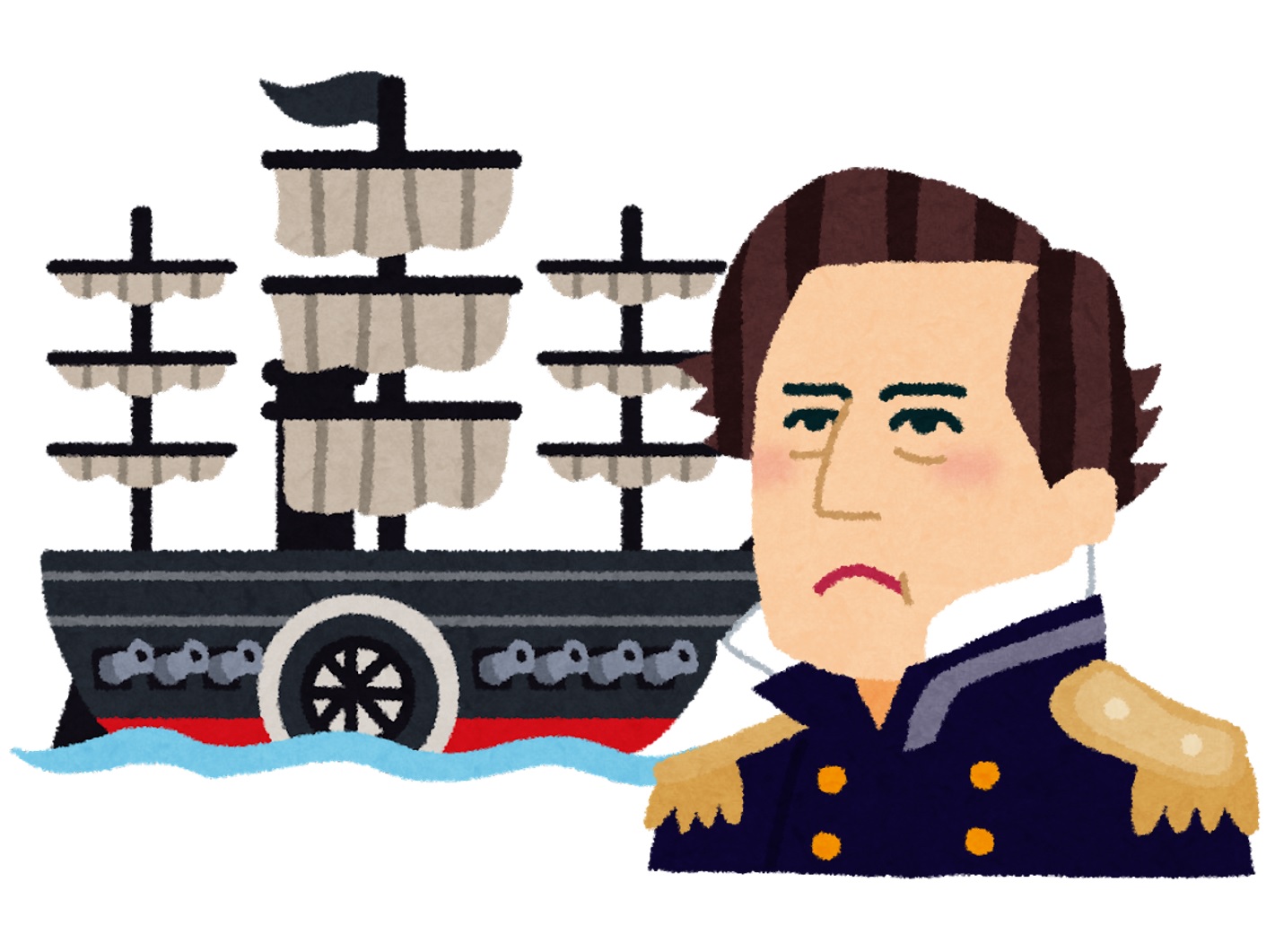





コメント