動物由来の言葉を集めました。
ネコババ
 「ネコババ」=猫ババ、猫のフン、という言葉の由来は、猫の習性に基づいています。猫は糞をした後に砂をかけて隠す行動をします。この行動が「悪いことを隠して知らん顔をする」という意味に結びつき、「猫ばば」という言葉が生まれました。
「ネコババ」=猫ババ、猫のフン、という言葉の由来は、猫の習性に基づいています。猫は糞をした後に砂をかけて隠す行動をします。この行動が「悪いことを隠して知らん顔をする」という意味に結びつき、「猫ばば」という言葉が生まれました。また、「猫ばば」の「ばば」は幼児語で「糞」を意味し、江戸時代後期頃から使われ始めたとされています。また、猫好きの老婆が借金を返さなかったことから「猫婆」と呼ばれ、それが転じて「猫ばば」という言葉になったという説もあります。
犬死に(いぬじに)
 「犬死に」という言葉が「何の成果も残さない、無意味な死」という意味になったのは、「犬」がかつて役に立たないものや無駄なものの象徴として扱われていたことに由来すると言われています。
「犬死に」という言葉が「何の成果も残さない、無意味な死」という意味になったのは、「犬」がかつて役に立たないものや無駄なものの象徴として扱われていたことに由来すると言われています。さるぐつわ
 さるぐつわ(=猿轡)は、馬具の一つである「轡(くつわ)」に関連しています。「轡」は馬の口に噛ませて手綱をつける金具を指しますが、これが「猿」に結びついた理由にはいくつかの説があります。
さるぐつわ(=猿轡)は、馬具の一つである「轡(くつわ)」に関連しています。「轡」は馬の口に噛ませて手綱をつける金具を指しますが、これが「猿」に結びついた理由にはいくつかの説があります。一説には、猿が厩(うまや)にいるだけで馬が落ち着くという昔のエピソードから、「猿」と「轡」が結びついたと言われています。
「猿ぐつわ」は声を出せないようにする道具としての意味も持ち、布や紐を口に噛ませて後頭部で縛る形状が一般的です。
トラになる
 酔っ払いのことを俗語で「虎」といい、「虎になる」とは酔っぱらって手がつけられない状態になること。その由来には諸説あります。
酔っ払いのことを俗語で「虎」といい、「虎になる」とは酔っぱらって手がつけられない状態になること。その由来には諸説あります。
- 泥酔した人が四つん這いになり、まるで虎のように見えることから。
- 酔った人が首を左右に振る様子が、張り子の虎の動きに似ていることから。
- 酔って暴れる姿が猛獣である虎のイメージと重なることから。
いずれにしてもお酒はほどほどに…。
いたちごっこ
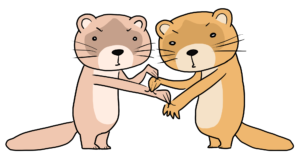 この言葉の由来は、江戸時代に流行した子供の遊びにあると言われています。この遊びでは、二人が向かい合い、「いたちごっこ、ねずみごっこ」と唱えながら、相手の手の甲をつねり、自分の手をその上に乗せるという動作を交互に繰り返します。この際限のない遊びが、「同じことを繰り返して決着がつかない状態」を象徴するようになり、現在の意味へと転じたのです。また、もともと鼬(いたち)や鼠(ねずみ)が非常に素早く動く様子が、この遊びの動作に似ていることから遊びの名前が付けられたとも言われています。
この言葉の由来は、江戸時代に流行した子供の遊びにあると言われています。この遊びでは、二人が向かい合い、「いたちごっこ、ねずみごっこ」と唱えながら、相手の手の甲をつねり、自分の手をその上に乗せるという動作を交互に繰り返します。この際限のない遊びが、「同じことを繰り返して決着がつかない状態」を象徴するようになり、現在の意味へと転じたのです。また、もともと鼬(いたち)や鼠(ねずみ)が非常に素早く動く様子が、この遊びの動作に似ていることから遊びの名前が付けられたとも言われています。
狐の嫁入り
- 昔の人々は、晴れているのに雨が降るという不思議な現象は、狐が人間を化かしていると考えたため、この名前がついた。
- 夜間に見られる「狐火」という現象が、嫁入り行列の提灯のように見えることから、きっと狐が嫁入りの行列をしていると考えられた。 などです。

馬の骨
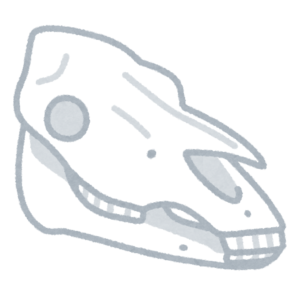 中国の古典にあることわざ「一に鶏肋(けいろく)、二に馬骨」に基づいています。このことわざでは、「鶏肋」は鶏の肋骨を指し、小さすぎて役に立たないものを意味し、「馬骨」は馬の骨を指し、大きすぎて処分に困るものを意味します。
中国の古典にあることわざ「一に鶏肋(けいろく)、二に馬骨」に基づいています。このことわざでは、「鶏肋」は鶏の肋骨を指し、小さすぎて役に立たないものを意味し、「馬骨」は馬の骨を指し、大きすぎて処分に困るものを意味します。
この背景から、「馬の骨」は役に立たないものや素性が不明なものを指す比喩として使われるようになりました。現代では、「どこの馬の骨ともわからない」という形で、身元が不明な人を軽蔑的に表現する際に使われることが多いです。
(馬に由来するその他の言葉は → 「馬に関連する言葉の由来」参照)
豹変(ひょうへん)
 この言葉の由来は中国の古典『易経』にあります。『易経』中の一節「君子豹変す、小人は面を革む」に由来しています。この表現は、豹(ヒョウ)の毛が季節によって抜け替わり、模様がより鮮やかになることを例えにしています。つまり、君子は自分の過ちを認め、良い方向に迅速に変わることができるという意味です。
この言葉の由来は中国の古典『易経』にあります。『易経』中の一節「君子豹変す、小人は面を革む」に由来しています。この表現は、豹(ヒョウ)の毛が季節によって抜け替わり、模様がより鮮やかになることを例えにしています。つまり、君子は自分の過ちを認め、良い方向に迅速に変わることができるという意味です。もともとはポジティブな意味で使われていましたが、現代では「態度や言動が急激に変わる」というニュートラルまたはネガティブな意味で使われることも多いようです。
たぬき寝入り
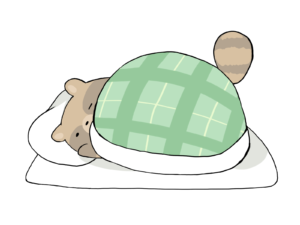 この言葉はタヌキ(狸)の習性に基づいています。タヌキは驚いたり危険を感じたりすると、死んだふりをして身を守ることがあります(実際は気絶してしまうそうです)。この行動が「寝たふりをする」という意味に結びつき、「狸寝入り」という表現が生まれました。
この言葉はタヌキ(狸)の習性に基づいています。タヌキは驚いたり危険を感じたりすると、死んだふりをして身を守ることがあります(実際は気絶してしまうそうです)。この行動が「寝たふりをする」という意味に結びつき、「狸寝入り」という表現が生まれました。
江戸時代の文献にも「狸寝入り」という言葉が見られ、当時から「都合の悪い時に寝たふりをする」という意味で使われていたようです。
以上、「そうだったのか語源の謎」日本語倶楽部編(河出書房新社刊)、「目からウロコの日本語語源辞典」Gakken、Chat GPTなどを参考にしました。


」「者(しゃ)」キャッチ-120x68.png)

コメント