とりたて助詞「こそ」についてまとめます。
「係助詞」
 「こそ」は古典文法では「係助詞(かかりじょし、けいじょし)」に分類されていました。係助詞とは、前に係助詞を使うと、その文の述語を一定の形で結ぶ文法形式です。例えば「今別れん」に係助詞「こそ」を入れ強調すると述語は已然形「別れめ」になり、単なる強調ではなく独特の意味の深さを与えます。
「こそ」は古典文法では「係助詞(かかりじょし、けいじょし)」に分類されていました。係助詞とは、前に係助詞を使うと、その文の述語を一定の形で結ぶ文法形式です。例えば「今別れん」に係助詞「こそ」を入れ強調すると述語は已然形「別れめ」になり、単なる強調ではなく独特の意味の深さを与えます。
「今別れん」→「今こそ分かれめ」
「とりたて助詞」としての「こそ」
前述のように「こそ」はもともと係助詞、それも典型的な係助詞であったために、現代日本語で「とりたて助詞」となり「係り結び」の原則は失われたものの、文型と機能の対応関係が比較的はっきりしています。そのようなことから「こそ」の意味について「文型」ごとに例文で確認してみましょう。
初中級レベルの「こそ」
①〔名詞Ⅰ〕+こそ、〔名詞Ⅱ〕だ。
①の文型で「究極のモノが〔名詞Ⅰ〕であること」を表します。
- これこそ本物だ。
- ライオンこそ百獣の王だ。
②〔時を表す名詞〕+こそ、~。
②の文型で「話者の決意、期待を強く期する時期」を示します。
- 今度こそダイエットを成功させよう。
- 今学期こそ、N1に合格するぞ。
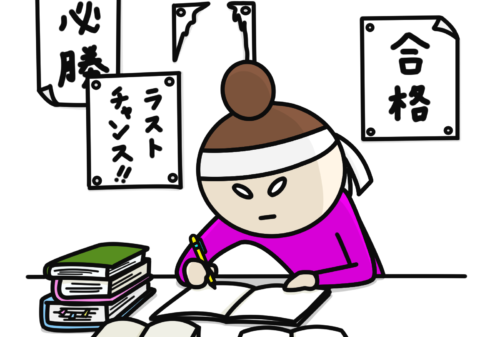
上級(N1)レベルの「こそ」
③〔~ば、から、~て、など〕+こそ、~。
③の文型では「~の記述を成立させる重要な要因、条件」を示します。
- あなたがいればこそ、ここまで頑張ってこれた。
- 今だからこそ、笑って話せることがある。
- 雪あってこその北海道だ。
④A+こそあれ、B
④の形では「Aのような状況はあるにはあるが、ほぼBだ」ということを示します。
- 彼の日本語は小さい間違いこそあれ、ほぼ完ぺきだ。
- 彼の日本語は小さい間違いこそあれ、大きな間違いはない。
- 苦労こそあれ、介護の仕事はやりがいがある。
- 苦労こそあれ、介護の仕事に楽しみはない。
⑤A+こそすれ、B+〔否定辞〕
⑤の形では「Aということはあり得ても、Bは絶対にありえない」ということを示します。
- 彼女には感謝こそすれ、恨みなどまったくありません。
- 彼は遅刻こそすれ、来ないことはない。
- 彼のやったことはほめられこそすれ、非難されることはない。
⑥「~こそ~」〔逆接接続詞〕、~
⑥の形で「前件は認めるものの、それと同等以上の重みをもつ後件が確実に成立する」ことを示します。
- 数こそ少ないが、わが校にも優秀な学生はいる。
- 先生は怒りこそしなかったが、相当気分を害していたようだ。
- 彼は成績こそまあまあだが、人間性とマナーが悪すぎた。
以上、NAFL日本語教師養成プログラム⑩日本語の文法ー基礎(山内博之著)アルク社などを参考にしました。




コメント