人名(日本人)由来の言葉を集めました。
カーディガン

カーディガン
「カーディガン(cardigan)」という言葉の語源は、イギリスのカーディガン伯爵 に由来しています。19世紀半ば、カーディガン伯爵はクリミア戦争(1853-1856年) においてイギリス軍を指揮しました。この戦争の際、兵士たちは寒さをしのぐために、前開きのニットの上着を着ていました。これが後に「カーディガン」と呼ばれるようになったのです。カーディガン伯爵自身がこの衣服を発明したわけではありませんが、彼の名がついたのは、このスタイルの軍服を採用したことが理由とされています。現在では、ボタンやジッパーで前を開閉できるニット製の上着を「カーディガン」と呼び、ファッションアイテムとして広く普及しています。
サンドイッチ
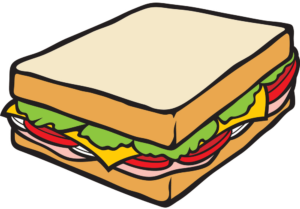
サンドウィッチ
「サンドイッチ(sandwich)」は、イギリスの貴族「サンドウィッチ伯爵(John Montagu, 4th Earl of Sandwich)」 に由来しています。18世紀、第4代サンドウィッチ伯爵 ジョン・モンタギュー は、食事の時間を惜しんで仕事や賭け事、特にカードゲームに没頭していました。彼は、片手で食べられるようにパンの間に肉を挟んだ料理を好んで注文していたといわれています。これを見た周囲の人々が、「伯爵と同じもの(the same as Sandwich!)」と頼むようになり、やがてこの食べ物自体が「サンドイッチ」と呼ばれるようになったのです。ただし、パンに具材を挟むスタイルの食事はそれ以前から世界各地に存在していましたが、「サンドイッチ」という名称が広まったのは、この逸話によるものです。
シルエット
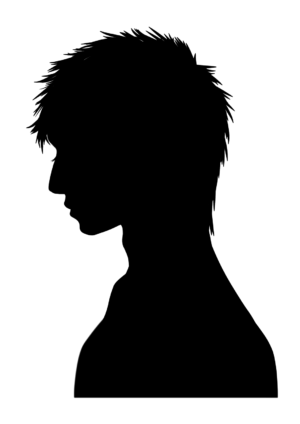
シルエット
「シルエット(silhouette)」は、18世紀フランスの財務大臣エティエンヌ・ド・シルエット(Étienne de Silhouette, 1709-1767) に由来しています。1759年、ルイ15世の財務大臣に就任した彼は、七年戦争による財政難を立て直すため、厳しい倹約政策を実施しました。しかし、その徹底ぶりが貴族たちの反感を買い、「ケチな財務大臣」として皮肉の対象となりました。当時、黒い紙で人物の横顔を切り取る影絵が流行しており、安価で簡単に作れることから「シルエット的=安上がりなもの」 という意味で彼の名前が使われるようになりました。次第に、影や輪郭だけを表現した図を「シルエット」と呼ぶようになり、現在の意味へと定着しました。つまり、「シルエット」という言葉は、財務改革によって「倹約」の象徴とされたシルエットの名前に由来するものです。
ボイコット
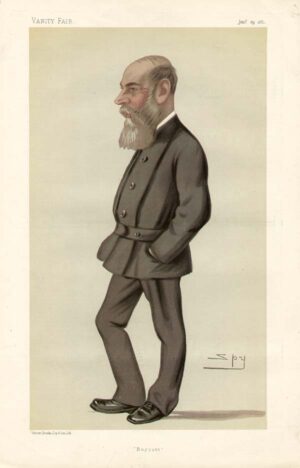
チャールズ・カニンガム・ボイコット(イギリス人1832-1897年)は、英国の土地差配人。アイルランドで自身が管理していた土地で、法外な額の借地料をその小作農に課しました。そのために、地元活動家たちが、ボイコット氏を地域社会から孤立させる目的で、工作農たちに労働を拒否するように促しました。このことから「ボイコット(する)」は、特定の商品の不買運動や、特定の人の排斥のために、会合や運動への参加を拒否したりすることを指す言葉となりました。
リンチ
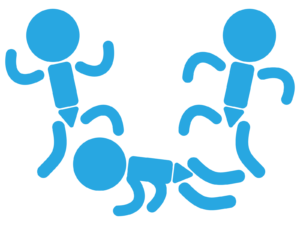 「リンチ(lynch)」という言葉の語源は、18世紀アメリカの人物に由来します。最も広く知られている説は、チャールズ・リンチ(Charles Lynch)という人物に関連しています。彼はアメリカ独立戦争時、バージニア州の地域で活動していた人物で、イギリス側の支持者や王党派を取り締まるために私的な裁判を行い、裁判を経ずに処罰を加えることがありました。このような私的な制裁行為が「リンチ法(Lynch Law)」として広まり、最終的に「リンチ」という言葉が使われるようになりました
「リンチ(lynch)」という言葉の語源は、18世紀アメリカの人物に由来します。最も広く知られている説は、チャールズ・リンチ(Charles Lynch)という人物に関連しています。彼はアメリカ独立戦争時、バージニア州の地域で活動していた人物で、イギリス側の支持者や王党派を取り締まるために私的な裁判を行い、裁判を経ずに処罰を加えることがありました。このような私的な制裁行為が「リンチ法(Lynch Law)」として広まり、最終的に「リンチ」という言葉が使われるようになりました
ギロチン
 「ギロチン(guillotine)」という言葉は、フランスの医師 ジョゼフ・ギヨタン(Joseph-Ignace Guillotin) の名前に由来しています。ギヨタンは、当時の斬首刑が斧や剣を用いるために苦痛を伴うことが多かったことから、より迅速で人道的な処刑方法 としてこの装置の導入を提案しました。実際の設計は外科医 アントワーヌ・ルイ(Antoine Louis) によって行われ、当初は「ルイゼット(Louison)」とも呼ばれていましたが、ギヨタンの名前が広まり、「ギロチン」という名称が定着しました。なお、ギヨタン自身は処刑機を発明したわけでも、ギロチンで処刑されたわけでもなく、1814年に自然死しています。それにもかかわらず、彼の名前はこの装置と結びつき、歴史に刻まれることになりました。
「ギロチン(guillotine)」という言葉は、フランスの医師 ジョゼフ・ギヨタン(Joseph-Ignace Guillotin) の名前に由来しています。ギヨタンは、当時の斬首刑が斧や剣を用いるために苦痛を伴うことが多かったことから、より迅速で人道的な処刑方法 としてこの装置の導入を提案しました。実際の設計は外科医 アントワーヌ・ルイ(Antoine Louis) によって行われ、当初は「ルイゼット(Louison)」とも呼ばれていましたが、ギヨタンの名前が広まり、「ギロチン」という名称が定着しました。なお、ギヨタン自身は処刑機を発明したわけでも、ギロチンで処刑されたわけでもなく、1814年に自然死しています。それにもかかわらず、彼の名前はこの装置と結びつき、歴史に刻まれることになりました。
摂氏

セルシウス
「摂氏(Celsius)」の語源は、スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウス(Anders Celsius, 1701-1744)に由来します。セルシウスは18世紀の科学者で、温度計の精度や気温の測定に関する研究を行いました。彼の業績で特に重要なのは、温度の測定基準を定めた「セルシウス温度尺度」の考案です。セルシウスは、温度を氷点(0度)と沸点(100度)に基づいて定義しました。この基準は、水の凍る温度を0度、沸騰する温度を100度に設定することにより、温度の変化を簡単に理解できるようにしたものです。セルシウス温度尺度は、特に気象学や科学の分野で広く採用され、後に彼の名前、セルシウスの中国語への音写「摂爾思」を取って「セルシウス」または「摂氏」と呼ばれるようになりました。
華氏
「華氏(Fahrenheit)」の語源は、ドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイト(Gabriel Fahrenheit, 1686-1736)の名前に由来する。ファーレンハイトは温度計の精度向上に貢献した科学者であり、1714年に水銀温度計を発明し、後に「華氏温度」を考案した。彼は当時使用されていた温度尺度の不正確さを改善するため、氷と塩を混ぜたときの最低温度を0度、人間の体温を約96度と定めた。その後、水の凝固点を32度、沸点を212度に設定し、これが現在の華氏温度の基準となった。日本では「華氏」の「華」は「ファー(Fah)」の音訳とされ、華氏温度は摂氏(Celsius)と対比される尺度として主にアメリカで使用され続けている。こうして、ファーレンハイトの名は温度単位として歴史に残り、「華氏」という言葉として定着した。「華氏」はファーレンハイトの中国読み「華倫海」から。
以上、新版「目からウロコの日本語「語源」辞典Gakken刊などを参考にしました。
.png)
-160x90.png)


コメント