日语综合教程第五册に採用された「住まい方の演出」(渡辺武彦著)第15章「庭」は原文の多くの部分が省略され、短くなっている。最も大きい削除部分を別途、読解資料として問題化し、速読用教材として教室で使用しました。
以下、元本「住まい方の演出」では「田舎料亭風の庭には困惑する」「”庭らしい庭”ではない雑木林への愛着」と題された二節である。
家のつくりがさまざまなように庭のありようもさまざまで、その間にはおのずから、なにがしかの調和が必要だ。
関西に石井修さんという住宅設計の名人がおられるが、数年前、縁あってこの方の一連の作を見学する機会を得た時、ぼくは住宅そのものの芸と品もさることながら、その庭のつくりが、主な庭園にとどまらず、通りすがりの廊下からチラリと見えるだけの植え込みにいたる隅々まで神経を行き届かせつつ、建物と見事に調和しているのに感嘆した。聞けば石井さんは「住宅だけでなく庭まで(それと家具はもちろんのこと)含めて一任されなければ設計を引き受けない」ことにしておられるそうで、これが住宅設計の理想だが、なかなかそこまで言いきれるものではない。ぼくも住宅の設計を業とする者の一人として、当然、自分の手がけた家にはそれと調和した庭をつくりたいのだが、これがそう思うままには行かないのである。
というのは、家を新築するとなると「庭だけは私にまかせてください」と言って、妙にいきいきと張り切っちゃう建築主がよくいるもので、これはとくに男性に多い。そう言われると、じゃお断わりしますとは言えないもので、かくして庭はしばしば設計者の管轄外になる。もちろん、それがかえって良い結果を生むこともあるのだが、これはちょっと困ったな、ということになる場合も少なくない。
それはたいてい、建築主が和風の立派な庭というものに中途半端な憧れを持っている場合である。自分にまかせて、と言っても実際に仕事をするのは植木屋さんで、建築主は植木屋の主人にあれこれ指図するだけだが、これがこの趣味の人には実に楽しいらしいのですね。で、まぁ、この場合もよい例外はあること認めたうえで言うのだが、だいたいにおいてこれは、ねじくれた松に笹の茂みとチマチマした石組を配して、田舎の料亭みたいな庭になっちゃう。日本人にはこういう庭こそ立派な、つまり“庭らしい庭”だと思いこんでいる人が多く、その固定観念の拡がりは実に深く広い。

言いにくいことながら、これは植木屋も悪いのだ。植木屋、と突然呼び捨てに変わったのは、好ましからざる類の人だけを区別して呼ぶつもりだからで、読者の中にこの職業にかかわる方がおられたら、自分は“植木屋さん”のほうだと思って怒らずに読みつづけていただきたい。
呼び捨てに値するほうの人は往々にして、庭好きの建築主の新築早々の気分の高揚につけこみつつ、やたらに高価な植木や庭石や灯籠などを売りつけ、建築とまったく釣り合わない庭をつくってしまうのである。ぼくは植木職の手になるいわゆる和風の造園をすべて否定しているわけでは決してなく、純和風の建物にしっくりした伝統的な庭の良さも心得ているつもりである。しかし、自分自身は和か洋かというような様式にこだわってはいないものの、ぼくが都市に設計する家に伝統的な純和風というものはまずないのに、それとまったく合わない松、竹、石組を持ちこまれることが多いので、つい憎まれ口をききたくなるのだ。植木屋という職業は日本ではいわば造園デザイナーの一種で、そうであるとするなら、いくら客の好みとは言え、建物に明らかに調和しない庭を唯々諾々とつくってしまう人が少なくないのはいかなる神経であろうか。
”庭らしい庭”ではない雑木林への愛着
しかし、こんなことがそういつもあるわけではなく、建物と庭との調和に理解がある住み手に一任され、話のわかる植木屋さんと出会って庭をつくるのは実に楽しい。この“話のわかる”という形容には微妙なニュアンスがある。というのは、ぼくは建物を主役として考えているから、たとえ一任されてもそう凝った庭を意図しないし、既存のものを再利用する場合を除けば庭石の類を使わないから、植木屋さんにとってあんまり良い商売にはならない。“話のわかる”とは、その辺を柔軟に対応してくれる人のことである。

雑木林風の庭園
これを具体的に言えば、普通の住宅の庭としてぼくが構想するのは、たいてい植木屋さんから見れば庭とも言えないような雑木の木立ちのようなものである。それもきちんと造園設計図を描くわけではなく、簡単なスケッチだけを材料にして「この辺に常緑の灌木が欲しいけど……」「ここにはヒョロッとした株立ちがあるといいんだけど……」「この隅には、なんか実のなる木を……」などと曖昧なことを言い、植木屋さんの意見を聞きながら樹種を決めていくのである。
これはまぁ、ぼくが造園の専門家のように植木に詳しくないせいもあるが、決して無知ゆえの便法というだけではない。ぼくだって株立ちというときには沙羅あたりかな、というくらいのイメージは持っているのだが、そう厳密に指定してしまうよりも、曖昧な指定で手持ちの木を使ってもらうほうがコストダウンしやすいし、また、もともとの構想が雑木林的なぼくの造園観からしても、それと似たものならなんでも良いや、というくらいの気持もあるからだ。ぼくの庭つくりはこのこと以外にたいした狙いがあるわけではなく、「常緑の灌木」というのはたいていブロック塀などを隠すためにすぎないし、「実のなる木」というのは、人間が食べられないものでも小鳥がよってくればそれも庭の一つの風情になるだろう、というだけのことである。
これは設計者としての発言というより個人的趣味の範疇になるだろうが、ぼくがこのような雑木林的な庭を好むのは、そのさり気なさがどんな建物にも調和するからでもあり、さらには、四季折々の風情を映し出す点で、様式の整った庭よりも例の治癒効果に優れているようにも思えるからだ。この好みには長年見慣れた父母の庭の影響もあるかもしれない。そういう気持ちで想像すると、庭そのものについては具体的な描写に乏しい『庭の砂場』でも、あの主人公が眺めているのも、やはり整った和風庭園ではなく雑木林的なさり気ない庭であると思えるのだ。
〔確認問題〕
(1)住宅設計家の石井修氏が設計を引き受ける条件はどれですか。
1.特にない 2.住宅のみを設計
3.住宅、庭を任せる 4.住宅、庭、家具を一任
(2)「庭だけは私に任せてください」という建築主はどんな人ですか、一番適切なものをえらんでください
1.田舎の料亭のような庭が好きな人 2.和風の立派な庭に憧れを持っている人 3.人に指図するのが好きな人 4.あまりお金を使いたくない人
(3) 筆者にとっての“話のわかる”植木屋さんとして、あてはまらないのはどれですか?
1.手持ちの木を使ってくれる 2.高価な材料を使いたがらない
3.指示通りの木や庭石を用意してくれる 4.意見、提案をしてくれる
(4) 筆者はどのような庭を造りたいと考えていますか。
1.和風の立派な庭 2.田舎の料亭のような庭
3.庭石や灯籠のある庭 4.雑木の木立ちのような庭
(5) 筆者がここで述べているような庭を好む理由として正しくないのはどれ
1.いろいろな建物に調和するから 2.筆者の主張する治癒効果に優れるから
3.父母の庭がそうだから 4.小鳥が寄ってくるから
解答:(1)4.(2)2.(3)3.(4)4.(5)4.
ちなみに、上記文章は、本ブログ記事の中では「庭」渡辺武信Ⅲ、とⅣ の間に入ります。


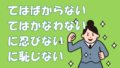
コメント