動物由来の言葉を集めました。(その2) 1はこちら → 動物由来の言葉1
牛耳る(ぎゅうじる)
組織を意のままに操縦する 「会社を牛耳る」
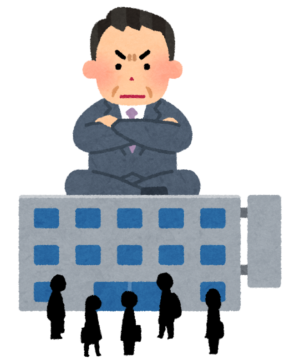 中国春秋時代、諸侯が盟約を結ぶ儀式をするとき、盟主となる人が、いけにえの牛の耳を裂き、その生き血を諸侯が順にすすって同盟を誓い合ったという習慣からきたものとされています。
中国春秋時代、諸侯が盟約を結ぶ儀式をするとき、盟主となる人が、いけにえの牛の耳を裂き、その生き血を諸侯が順にすすって同盟を誓い合ったという習慣からきたものとされています。 その習慣「牛耳を執る(とる)」の「牛耳」に「る」をつけ動詞化したものが定着しました。
この「牛耳る」の成立は比較的新しく、大正初期からと言われています。一説には、旧制高校の生徒たちが使ったスラングから出たものとも言われています。
この「牛耳る」の成立は比較的新しく、大正初期からと言われています。一説には、旧制高校の生徒たちが使ったスラングから出たものとも言われています。
猫の手も借りたい
非常に忙しく人手不足なようすをたとえて言う言葉。「年度末は猫の手も借りたいぐらい忙しい」
 かつて猫は、家の中で悪さをするネズミを捕まえてくれるという役割がありましたが、最近の猫はネズミを捕まえなくなりました。犬は飼い主に忠実に、侵入者がおれば追い払ってしてくれます。
かつて猫は、家の中で悪さをするネズミを捕まえてくれるという役割がありましたが、最近の猫はネズミを捕まえなくなりました。犬は飼い主に忠実に、侵入者がおれば追い払ってしてくれます。役に立つことを、何一つしない猫ですが、そんな怠惰な猫の手であっても借りたいぐらい忙しい、という意味で使います。
といっても、最近の言葉ではなく、江戸時代の浄瑠璃「関八州繁馬」に、
「下までおめでた事、猫の手もかりたい忙しさ」というセリフが登場します。
猿も木から落ちる
その道に長じた人でも、時には失敗することがあるというたとえ。
 猿といえば、木登りが得意な動物。そんな猿でも油断すれば木から落ちてしまう。
猿といえば、木登りが得意な動物。そんな猿でも油断すれば木から落ちてしまう。 よく似た言葉に「弘法にも筆のあやまり」「河童の川流れ」「上手の手から水が漏れる」などがあります。これらはすべて、得意な分野であっても油断すると失敗するということへの戒めとして使われます。これだけさまざまな方言があるということは、物事に長けて、上達しても、気を抜いてしくじってしまう人が、いつの時代も多いのだ、ということを示しているようです。注意しましょう。
虎の威を借る狐(とらのいをかるきつね)
他の権勢に頼って威張る小人物のたとえ
 中国「戦国策₋楚策」にある寓話によります。
中国「戦国策₋楚策」にある寓話によります。 虎が狐をつかまえて食べようとしたところ、狐がこう言います。
「私は天帝の使いです。だから私を食べると天帝に背くことになりますよ。その証拠に私の後をついて来てごらんなさい」
「私は天帝の使いです。だから私を食べると天帝に背くことになりますよ。その証拠に私の後をついて来てごらんなさい」
虎はそれを聞いていっしょに行くと、すべての獣が皆恐れて逃げ出します。虎は獣たちは自分を恐れて逃げ出しているということを知らず、愚かにも狐の言う通りだと納得してしまう。
まとめ(表)

以上、新明解語源辞典(三省堂)などを参考にしました。




コメント