第十回遣唐使(752年)

鑑真(688ー763年)
第10回遣唐使は藤原清河を大使として752年に出発した。この使節は、朝貢の場で新羅と席次争いをしたことで知られる。各国からの使者は宮殿内で東西に分かれ整列する。東がいわゆる東側諸国、西側に中央アジア諸国を中心とした国々が並ぶ。当初、東のトップが新羅、西のトップが吐蕃であった。これに対し日本は、「新羅は古くから日本に朝貢している。よって日本が新羅より席次が下であるのは矛盾している」と主張し、結果、新羅は吐蕃の次席に移動、東の主席は日本になった。
さらに第10回遣唐使で有名なのは鑑真を来日させるために動いたということである。藤原清河は、鑑真来日の許可を玄宗に申し出、許可を得ようとした。玄宗は積極的で、鑑真以外に道士の渡日も提案してきた。当時の日本では道教は振るわず、これを広める意図はなかったので日本側は玄宗の提案を断った。結局、鑑真は副使大伴古麻呂の乗る船に密航のかたちで乗り込み、753年ついに日本の土を踏む。
安史の乱(755年)
755年、安史の乱が勃発する。節度使として辺境警備にあたっていた安禄山が挙兵、長安を占領する。皇帝・玄宗は蜀へ逃れ、混乱の中で皇太子が即位し粛宗となった。安禄山は自ら皇帝を名乗るが、部下に殺害され、その後は史思明が反乱を引き継いだ。最終的に763年、唐とウイグル帝国の援軍により鎮圧されるが、この乱は唐の衰退を加速させる結果となった。
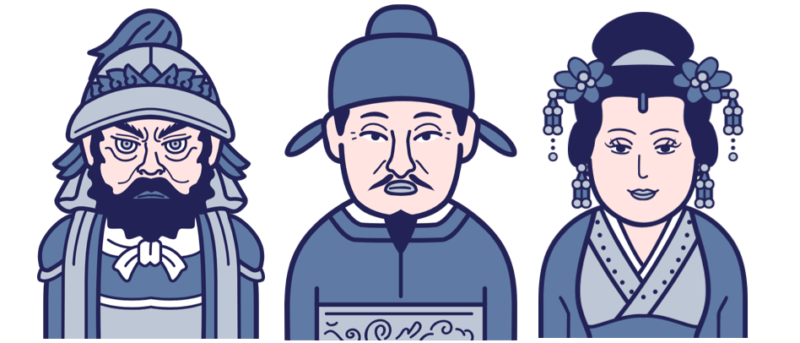
安禄山(703ー757年)玄宗皇帝(685ー762年)楊貴妃(719ー756年)
反乱の背景には、節度使の権力拡大と唐の政治腐敗があった。辺境防衛を担う節度使が強大な軍事力を持つ一方で、宮廷では宦官や楊貴妃の影響が強まり、政治は混乱した。加えて戦乱による人口減少と財政悪化により、唐は弱体化し、地方の節度使が半独立状態となる「藩鎮」体制が形成された。安史の乱は、単なる反乱にとどまらず、唐の統治構造を大きく変える歴史的転換点となったのである。
第十一回遣唐使(759年)
日本は758年、渤海からの使者により安史の乱を知る。第11回の遣唐使は、安史の乱の報を得た日本が、唐に残留していた藤原清河を迎えるためのものであった。藤原清河は阿倍仲麻呂を伴って帰国途上、逆風に遭いベトナムに漂着、仲麻呂と共に長安に戻っていた。
この時の日本から遣唐使を、安史の乱後の国情偵察とみた唐は、清河の帰国を許さなかった。そして、渤海を通じて再び、混乱した唐の状況を知り、日本はいったん遣唐使の派遣を中止する。
道鏡の宇佐八幡宮神託事件(769年)
大陸で安史の乱が起こり、唐の繁栄に陰りが見えかけた頃、日本では仏教にまつわる象徴的な事件が起こっていた。僧である道鏡は、称徳天皇の寵愛を受け、政界で強い権力を握った。彼に関連する事件として最も有名なのが「宇佐八幡宮神託事件」(769年)である。
道鏡は法王に就任し、さらに天皇の位を狙ったとされる。769年、宇佐八幡宮から「道鏡を天皇にすれば天下は安泰である」という神託が下ったという報告がある。これに対し反道鏡派が和気清麻呂を遣わし再度神託を聞くと「皇位は皇族が継ぐべき」との。これにより道鏡の野望は阻止され、彼は失脚し下野国(現在の栃木県)へ流された。

道鏡(700ー772年)称徳天皇(718ー770年)和気清麻呂(733ー799年)
この事件自体は一人の僧侶と女帝称徳天皇が原因となったものである。が、聖徳太子以来、仏教を中心に国を治める中で、仏教の勢力が強くなりすぎ、政治介入していく中でこのような事件が起きた。奈良時代後半の社会問題を象徴するような出来事であった。
第十二、十三回遣唐使(775、778年)
唐の国情安定後、775年に第十二回、778年に第十三回遣唐使が派遣される。第十二回では出発前に使節間で争いが生じたり、長安に到着後も安禄山の乱による疲弊などを理由に入京人数が限られたりし、みるべき成果は得られなかったようだ。また第十三回も唐からの客人を送り届けるのが主目的のものであった。
第十四回遣唐使(801年)
日本では781年第50代桓武天皇が即位する。桓武天皇は784年平城京を棄て長岡に都を移す。さらに794年には平安京へと遷都する。平安時代の始まりである。桓武天皇が遣唐使を任命したのは801年、即位から二十年後のことである。平安遷都から七年、都造営にもめどがつき実行された。
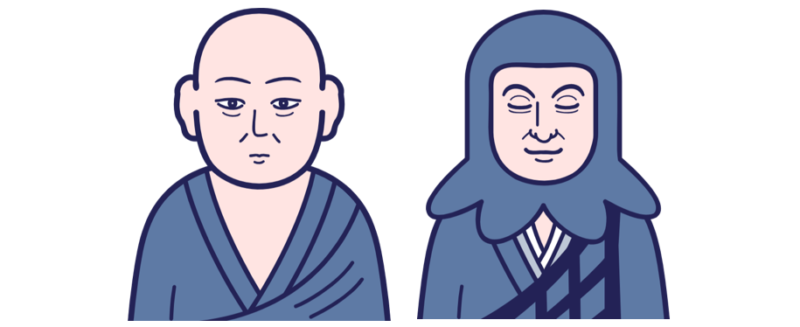
空海(794ー864年)最澄(774ー835年)
第十四回遣唐使船の第一船は1か月以上も海上をさまよい、福州に到達した。この船には空海が乗船していた。一行が長安につくまでには出港から四か月を要した。また第二船は明州(寧波)に到着する、この第二船には最澄が乗っていた。最澄は長安へ向かわず天台山へ向かっている。
第十五回遣唐使(838年)

円仁(794ー864年)
第十四回遣唐使船では、最澄の愛弟子ともいえる円仁が参加している。のちに天台座主となる円仁は「入唐求法巡礼行記」により詳細な記録を残している。円仁はなぜか入京を許されなかった。そこで円仁は、他の使節との帰国をせずひそかに唐に残る。
円仁はまず五台山に巡礼し、続いて長安で修業に励んだ。長安滞在中に武宗(在位840-846年)が仏教弾圧を開始、円仁も還俗させられる。帰国の便を求めて山東半島に移動。赤山にいた時武宗が死去し、仏教弾圧が終了する。円仁は再び剃髪し僧侶となった円仁は847年新羅商人の船に乗船し帰国の途に就く。
遣唐使の中止(894年)
第15回遣唐使から半世紀、かつての遣唐使の記憶が薄れていく中で、最後の遣唐使派遣計画が持ち上がった。大使に任命されたのが菅原道真(845-903年)である。しかし894年菅原道真は、遣唐使派遣の白紙撤回を奏上する。当時の唐は大規模農民反乱「黄巣の乱」を経て、その衰退は決定的なものとなっていた。その後、朱全忠が唐を滅ぼし、五代十国時代の混乱へとつながる。ここにおいて二百五十年以上におよんだ遣唐使の時代は終わりを告げる。
以上、「古代日中関係史」河上麻由子著(中公新書)、「遣唐使」東野治之著(岩波新書)を参考、引用させていただきました。





コメント