いろいろな台所用品の語源について調べました。
まな板(俎板)
食材を包丁で切るときに下に置く板のこと。
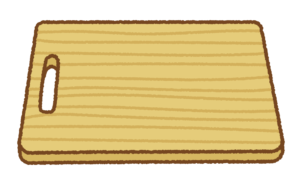 「まな」は「真魚」と書き、食用の魚の意味。「な」だけでも「魚」の意味ですが、「な」は別に食用植物をも指したので、特に魚であることを明確にするときは「本当の、真の」という意味の接頭語を伴った「真魚」という語を用いたとされます。したがって、「まないた」は魚をさばくための板、が原義。
「まな」は「真魚」と書き、食用の魚の意味。「な」だけでも「魚」の意味ですが、「な」は別に食用植物をも指したので、特に魚であることを明確にするときは「本当の、真の」という意味の接頭語を伴った「真魚」という語を用いたとされます。したがって、「まないた」は魚をさばくための板、が原義。包丁
料理に使う刃物の総称。
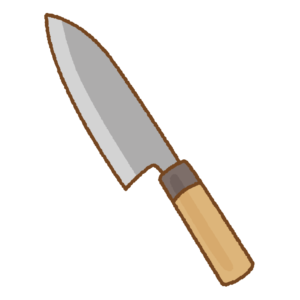 「包丁(ほうちょう)」の語源は、古代中国に由来しています。もともとは「庖丁」と書き、「庖」は台所や調理場を意味し、「丁」はその仕事に従事する男性を指していました。つまり、「庖丁」は「料理人」を意味していたのです。
「包丁(ほうちょう)」の語源は、古代中国に由来しています。もともとは「庖丁」と書き、「庖」は台所や調理場を意味し、「丁」はその仕事に従事する男性を指していました。つまり、「庖丁」は「料理人」を意味していたのです。また、中国の古典『荘子』には、名人の料理人「庖丁」が登場します。彼が牛を見事に解体する技術を披露したことから、その際に使われた刃物が「庖丁」と呼ばれるようになったという説もあります。
日本に伝わった後、平安時代には「庖丁」が料理人を指す言葉として使われていましたが、やがて料理に使う刃物全般を指すようになり、室町時代頃から「庖丁刀」の「刀」が省略されて現在の「包丁」という形になったとされています。
しゃもじ(杓文字)
飯をよそう道具。
 「しゃもじ」の語源は、もともと「杓子(しゃくし)」と呼ばれていた道具に由来します。「杓子」は柄の先に皿状の部分が付いた道具で、ご飯や汁物をすくうために使われていました。これが女房詞(にょうぼうことば)として変化し、「しゃもじ」と呼ばれるようになったのです。
「しゃもじ」の語源は、もともと「杓子(しゃくし)」と呼ばれていた道具に由来します。「杓子」は柄の先に皿状の部分が付いた道具で、ご飯や汁物をすくうために使われていました。これが女房詞(にょうぼうことば)として変化し、「しゃもじ」と呼ばれるようになったのです。
当初、「しゃもじ(杓文字)」は「飯杓文字」と「汁杓文字」のどちらをも指しましたが、のち、両者を区別するため、飯杓文字のほうを「おしゃもじ」、汁杓文字のほうを「お玉(杓文字)」と言い分けるようになりました。
また、広島県の宮島(厳島)がしゃもじ発祥の地とされています。宮島の僧侶が弁財天の琵琶の形に似たしゃもじを考案し、参拝者へのお土産として広めたことが始まりだと言われています。
はし(箸)
ものを挟んで食べるための一対の細い棒。
「箸(はし)」の語源にはいくつかの説があります。以下が代表的なものです:
- 「端(はし)」説: 箸の先端で食べ物を挟むことから、「端(はし)」が転じて「箸」になったという説。
- 「嘴(くちばし)」説: 古代の箸は鳥の嘴(くちばし)に似た形状をしていたため、「嘴」が語源となったという説。
- 「挟むもの」説: 箸の役割である「挟む」という動作から、その名前が派生したという説。
- 「橋」説: 箸が食べ物と口をつなぐ「橋渡し」の役割を果たすことから、「橋」に由来するという説。
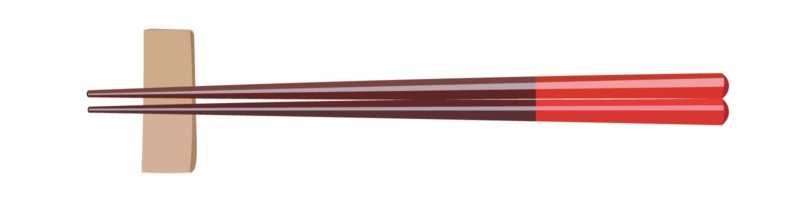
箸は古代中国から伝わり、日本では奈良時代頃に普及したとされています。現在では、食事の道具としてだけでなく、文化や礼儀作法にも深く関わる存在となっています。
おさら(お皿)
(食べ物を乗せる)浅く平らな器。
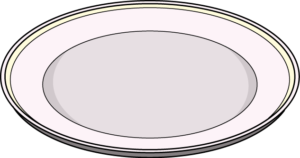 『和訓栞』に「あさらけ」の略語とあります。「あさ」は「浅」、「ら」は助辞、「け」は食器の意味の「笥(け)*」。すなわち「あさらけ」は浅い食器という意味になるといいます。この「あさらけ」の「あ」と「け」が脱落して、ていねい語の「お」がついて「おさら」になったというのが有力。ただ「あさらけ」の実際の用例は見つかっていないそうです。また、『正倉院文書』には「佐良気(さらけ)」という文字があります。
『和訓栞』に「あさらけ」の略語とあります。「あさ」は「浅」、「ら」は助辞、「け」は食器の意味の「笥(け)*」。すなわち「あさらけ」は浅い食器という意味になるといいます。この「あさらけ」の「あ」と「け」が脱落して、ていねい語の「お」がついて「おさら」になったというのが有力。ただ「あさらけ」の実際の用例は見つかっていないそうです。また、『正倉院文書』には「佐良気(さらけ)」という文字があります。 *万葉集の「家にあれば笥(け)に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る」(有間皇子)という歌はとても有名です。
ざる(笊)
竹、金属などを編んで作った皿型、鉢型の容器。
 『大言海』では古代語彙の「いざる」の「い」が脱落したものとしています。そして「いざる」は「湯去り」の転化だといいます。「湯が去っていく」ということでなるほどと思ってしまいます。ちなみに語頭の「い」は脱落しやすいといわれ、イダク(抱)→ダク、イバラ(薔薇)→バラ、など多数あります。
『大言海』では古代語彙の「いざる」の「い」が脱落したものとしています。そして「いざる」は「湯去り」の転化だといいます。「湯が去っていく」ということでなるほどと思ってしまいます。ちなみに語頭の「い」は脱落しやすいといわれ、イダク(抱)→ダク、イバラ(薔薇)→バラ、など多数あります。 ただ中国語のザルを意味する言葉に、中国の「笊籬(そうり)」という言葉に由来するという説もあります。「笊籬」は竹で編んだ器を指し、日本に伝わった際に「ざる」と転訛したと考えられています。「笊籬(そうり)」は中国語で「zhao li(ジャオリ)」。似てなくもないですね。
はち(鉢)
お皿より深くて、上が大きく開いた容器。
 「鉢(はち)」は、古代インドの梵語「Patra(パートラ)」(容器という意味)に由来します。この言葉は、本来仏教語で、僧侶が食事や托鉢の際に使用する円形の深い容器を指していました。日本に伝わった際に「鉢多羅(はったら)」と音訳され、さらに簡略化されて「鉢」となったとされています。
「鉢(はち)」は、古代インドの梵語「Patra(パートラ)」(容器という意味)に由来します。この言葉は、本来仏教語で、僧侶が食事や托鉢の際に使用する円形の深い容器を指していました。日本に伝わった際に「鉢多羅(はったら)」と音訳され、さらに簡略化されて「鉢」となったとされています。 《参考》丸い形が特徴で、たとえば「鉢合わせする」という慣用句は「鉢の形の頭(頭蓋骨)が出合い頭にお互いぶつかる」というイメージからできた言葉です。
かま(釜)
飯を炊いたり、湯を沸かしたりする金属の器具。(釜)
 これも諸説あります。『大言海』では、「気間(けま)が転じて、烟気の意味」としています。「かま」はもともと「火を燃やす所」ということで、当然煙が生じます。『大言海』はそこに語源を求めたことになります。
これも諸説あります。『大言海』では、「気間(けま)が転じて、烟気の意味」としています。「かま」はもともと「火を燃やす所」ということで、当然煙が生じます。『大言海』はそこに語源を求めたことになります。 一方、朝鮮語の「kama」と同源という説もあります。
「かまど(竈)」は「かま」のある所ということで、「ど」は「所」の意味の「と」の連濁。また「しおがま」は塩を焼いて作る所で、こちらの「かま」には「竃」の字をあてることが多いです。
現在「かま」というと、「釜」の他に、陶器などを焼く装置である「窯(かま)」、火で水などを熱する装置である「罐(かま)」などがありすべて同源。「かま」にもいろいろありますね。
とっくり(徳利)
酒などを入れる、細長く口のせまい容器。

徳利とお猪口
「とっくり」は「とくり」の変化したもの。漢字は「徳利」のほか「得利」、「土工李」などの表記がありますが、いずれも当て字。語源はわかっていないですが、いかにも擬音から生まれたように思われます。
容器の口が狭いので、そそぐとき「トクトク」「トクリトクリ」と音がするところから、名付けられたとするのが妥当でしょう。
またとっくりのお酒を受ける容器を「おちょこ(お猪口)」といいますが、こちらも語源不明。「ちょく」の音が変化したものですが、「鐘(zhong)」の呉音に由来する説がありますが、詳細はわかりません。「猪口(ちょこ)」と書き、猪の口に似ているからと言う人もいますが、そもそも「猪口」が、当て字っぽいのでこれは信用できません。
以上、新明解語源辞典(三省堂刊)などを参考にまとめました。




コメント