明治35年(1902年)帰国(続き)
漱石は悩み続ける。漱石、そして漱石の時代の若者の悩みを、現代のわれわれが理解するのは難しい。日本は一千年以上、隣国中国の文明を規範として発展してきた。明治維新を経て欧米という、もう一つの中心に属する国となろうとした。明治政府は欧米文明の受け入れ口を、効率性のためにまずは東京に限った。より正確に言えば東京帝国大学が中心になって、欧米のすべてを学び取り、自分たちのものにしようとした。そのため、帝国大学には破格の待遇をもって多くの欧米の学者を招待し、日本全国から集まったエリートたちに学ばせた。明治前半はひたすら学ぶ時代であった。
.jpg)
華厳の滝(栃木県)
漱石の時代、明治後半は学んだものを元に、新しい日本のシステムを構築する時代だ。その作業は、工学、医学分野では比較的簡単だったかもしれない。しかし思想、哲学、文学の分野に関わるシステムは、はっきりと目に見えるようなものではないが、その民族の生きる意味、規範のようなものだ。それも自然科学のように高きから低所に向け、自然に水が流れるような伝播ではなく、取捨選択も必要だ。一方的に欧米的なものを受け取るだけでなく、たとえば仏教や儒教のように、価値ある部分を残しつつ、欧米の合理主義、個人主義の良い部分をうまく消化し、取り入れ、新しい規範をつくりあげてゆく作業が必要であった。新しい時代、個人としてどう生きるべきか、そして国家はどうあるべきか、当時の日本のエリート層は悩める人々の群れであった。
漱石が英国から帰国した翌年、漱石の教え子だった一高生、藤村操(みさお)は「万有の真相は不可解。」と書いた遺書を残し、華厳の滝で自殺。後を追うものが続出した。明治末期は、近代日本の最後の産みの苦しみの時期であった。
帰国後
ともあれ、留学期間は終わった。漱石は多少英国嫌いになったかもしれない。明治36年、漱石は帰国する。彼は熊本へは復職せず、第一高等学校と帝国大学英文科講師を兼ねることになる。律儀に講義に打ち込んだ漱石は、過労から再び精神の状況を悪くしていった。松山時代が終わった明治28年、見合い結婚をしてすでに二人の女児をもうけていたが、妻鏡子によると、漱石の神経衰弱はこの頃が最も悪かったという。その頃は、家族に暴力をふるうこともあり、妻と子は一時漱石と別居生活をしていたこともあるという。
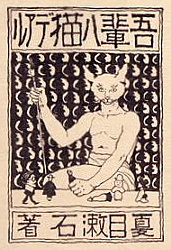
吾輩は猫である初版本表紙
そんな彼を救ったのは、正岡子規亡き後、子規中心に行われていた句会および文章の勉強会を引き継いでいた高浜虚子であった。虚子は、神経衰弱に悩む漱石に、気分転換に文章を書くことをすすめる。できあがってきた文は、題名もなく短いものだったが仲間内で評判がよく、虚子のアイデアで「吾輩は猫である」と名付けられた。同人誌「ホトトギス」に掲載され、大評判となり、連載ものとなり、結局長い作品になった。1905年38歳、やや遅咲きの小説家夏目漱石の誕生である。翌年「坊っちゃん」「草枕」を始めとする作品を発表するが、漱石はここで人生の大転換をする。大学を辞し、小説一本で身を立てようと決意するのだ。
ここでも、なんでも両立してやってのける森鴎外との差が出る。一高、東京帝国大学の講師という職を辞し、朝日新聞に入社し、専属の小説家として再スタートする。夏目漱石40歳、不惑の年である。東京大学教授の地位が確約されていた漱石であったが、世間的な地位、名誉にこだわらず、小説を書くことに専念することを選ぶ。
朝日新聞専属の小説家として
移籍後第一作となった「虞美人草」は、大人気となり漱石は一躍人気作家となる。以後、亡くなるまでの10年間で、前期三部作「三四郎」「それから」「門」、後期三部作「彼岸過迄」「行人」「こころ」、遺作となり未完で終わった「明暗」を始め、漱石作品のほとんどは、この時期に出来上がる。執筆の場所も定めた。漱石出生地にほど近い現在の南早稲田の地に新たに居を構え、「漱石山房」と名付けた。
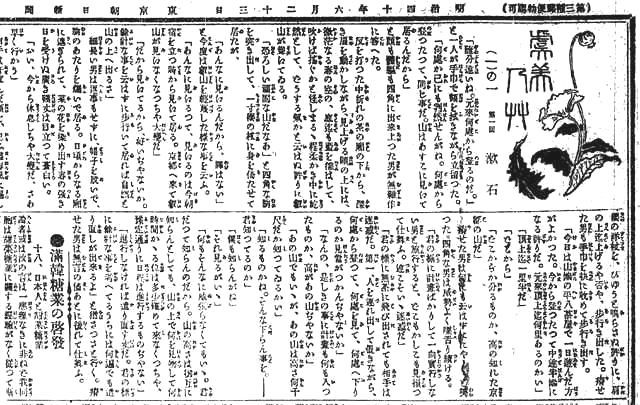
虞美人草(第一回、朝日新聞)
夏目文学の核となる作品群が次々と創作されたこの時期も、漱石のコンディションは決して良くなかった。それどころかさらに悪化する。43歳の時には、神経衰弱に加えて胃潰瘍を発症し入院。夏に転地療養のため、伊豆修善寺温泉に出かけるも、逆に病状悪化し、療養先で大量吐血し危篤状態にまでなる。漱石研究者の間ではこれを「修善寺の大患」と呼ぶ。なんとか一命をとりとめた漱石だが以後、入退院を繰り返す。修善寺の大患は前期三部作と後期三部作の間に当たり、この出来事を機に漱石の作品は、より重い人間の内面を描く作品に変化している。
漱石45歳の時、つまり明治45年7月、明治天皇崩御。明治が終わる。明治と共に生まれた漱石にとっても大きなできごとであったろう。明治と共に生きた漱石の作家活動は、大正時代になっても精力的に続けられた。翌年には神経衰弱、胃潰瘍の悪化を理由に「行人」の連載を一時中断しているが半年後に復活。次の大正3年には、夏目漱石の代表作ともいえる「こころ」を発表している。
「こころ」以後
「こころ」を書き終えた漱石は、再び入院。療養中の大正4年1月に随筆「硝子戸の中」を、6月に自伝的小説である「道草」を発表する。大正5年1月リューマチを発症し、療養のため湯河原へ赴くが、そこで新たに糖尿病の診断を受ける。それでも彼は書くことをやめなかった。5月「明暗」の連載を開始した。11月の門下生との集まりの中で「則天去私」という言葉について語る。「則天去私」とは「天の教えにのっとり、私を滅する」という意味。漱石はこれを理想の境地であると語った。門下生の中には芥川龍之介がいた。12月9日自宅で永眠。「明暗」は未完の遺作となった。

漱石山房バルコニーでくつろぐ漱石
写真の夏目漱石は、見慣れた千円札の夏目漱石とは別人のようだ。晩年の10年を暮らした漱石山房のバルコニーの椅子に座り庭を眺めている。表情は決して暗くはないが、やせ衰え、いかにも弱々しく見える。執筆を続け、疲れた時にこのバルコニーに出てゆったりしていたのだろう。残念なことに、彼の家は、東京大空襲で跡形もなく焼けてしまった。現在は写真などを元に復元され、漱石山房記念館として一般に公開されている。裏庭には「吾輩な猫である」のモデルとなった黒猫の墓もある。
このバルコニーに出て漱石は、好きな芭蕉を見ていたという。復元された家には写真の漱石の視線の先に、芭蕉が植えられている。
生誕の時を求めて
メトロ東西線早稲田駅すぐの漱石生誕の地から、終焉の地、漱石山房までは歩いて10分もかからない。漱石は、生まれた場所に戻ろうとしたのではないだろうか。江戸から明治へ。日本人のすべての価値観が180°転換することを余儀なくされた時代。新しい日本人の方向性を探し続けることに、公のためにその一生を捧げた漱石。真面目一徹を貫き通した漱石。疲れた頭を休めるため、バルコニーに出て、芭蕉を眺める時、彼の頭の中の片隅には、幸せに過ごした、母千枝との幼年時代の思い出のシーンがよみがえっていたにちがいない。





コメント